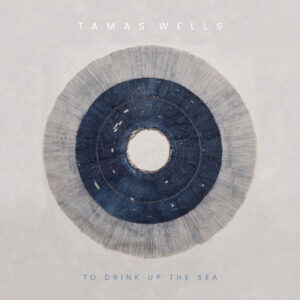「光が多いところでは、影も強くなる There is strong shadow where there is much light」
かの詩人ゲーテもこう言っているように、ミュージシャンが放つ輝きの傍には、いつも影を引き受ける人がいる。では、アジア・インディーズという分野において、その”影=黒子”のモチベーションはなんだろう。
この問いをぶつけるのに相応しい人といえば、大崎 晋作(おおさき・しんさく)さんの姿を思い浮かべる人は少なくないだろう。
大学(それも、かなり良い)を卒業後、東京渋谷に拠点を構えるレコード会社、株式会社インパートメントへ入社。「sad is beautiful」を合言葉に、悲しくも美しいフォーキーな音楽を届けるレーベルLiricoを立ち上げ、2017年にある出会いを機に、プム・ヴィプリットの日本展開を支えた。
プム・ヴィプリットといえばSUMMER SONICへ2回連続で出演し、アジア各国でのフェスのヘッドライナーを飾る時の人であるが、日本でもその情報を時差なく得られるのは大崎さんの尽力がベースにある。またプム・ヴィプリットだけではなく、シンガポールのSobsや台湾の緩緩 Huan Huan(ホァン・ホァン)、タイのナムチャら、アジアのアーティストのディストリビューションも手掛けている。
なので相当すごいことをやっているのだが、大崎さん自身は特に表舞台で発言するわけでも、SNSで目立つ動きをするわけでもなく、控えめな佇まいだ。
ミステリアスな大崎さんが、このたび19年間の会社員生活に終止符を打ち独立した。しかし音楽業界から出るわけではなく、これまで関わってきたアーティストたちとの関係は続いていくという。
アジアのアーティストが連帯し、大きな流れをつくる昨今、私たちにできることはなんだろう。という大きな問いは後半で聞いていくとして、まずはLiricoのプレイリストを聞きながら、黒子の世界に浸ってほしい。
サブカル英才教育×アウトサイダー志向で音楽業界へ
“田舎の高校生が体験するようなことじゃない。適当にもほどがありますよ(笑)”
Shinsaku Ohsaki
━━大崎さんにお話を聞こうと思ったのは、独立する背景が気になるとともに、プム・ヴィプリットというスターを手掛けた華やかな実績の、その本質に触れたいと思いまして。まずは音楽業界で働く前、感性の源流から伺えますか。
兵庫県加西市という、人口約5万人位のところに実家があります。大学に入学するまで実家暮らしで、当時はインターネットもほとんど普及していなかったので、音楽にアクセスする手段といえば、音楽雑誌を読む以外では電車やバスに乗って1時間ほどかけて姫路のタワーレコードに行くくらいでした。
よくありがちな、親がカルチャーが好きでその影響を受けて育ったという家庭環境ではありませんでしたが、どういうわけか兄はやたら音楽、映画、小説に詳しく、いわばサブカルの英才教育を施してくれたんです。お陰で中学入学の段階でレディオヘッドなどUS/UKロックを中心に聞いていました。当然親は訝しんでいましたけれど、兄は「英語の勉強になるからええねん!」とめちゃくちゃ適当なことを言って説得していましたね(笑)
初めて連れて行ってもらったライブは、いまは無き心斎橋クラブクアトロで行われたパルプ (Pulp)※ の来日公演でした。1996年のはじめ、僕が中学2年生のときのことです。そして、そのライブの前に見た、ジム・ジャームッシュ監督の『デッドマン』に大いに影響を受けました。モノクロで静かな西部劇の雰囲気は、『ジュラシックパーク』のような作品とは全く違っていたんです。
※パルプ (Pulp):1970年代にイギリスで結成され、90年代ブリットポップブームの主役と言われているバンド。

━━非主流な作品に惹かれる原体験だったんでしょうね。
その後は少し邦楽寄りになり、スーパーカー、くるりなどを中心に聞いていました。今でも覚えているのは、高校生のとき、サッカー部の部活を仮病で休んで行った、フジロックフェスティバルです。豊洲で行われた2回目のやつです。これも兄に連れて行ってもらったんですけどね。ミッシェルガンエレファントの出番でモッシュが起きて何度も中断するという、あの伝説の現場に居合わせました。懐かしいですね。
とはいえ現地集合・現地解散ですよ。携帯も普及していない時代、どうやって落ち合ったのかすら記憶にないですし、1日目と2日目の夜はホテルとかではなく全く知らない人の家に泊まらされましたね。田舎の高校生が体験するようなことじゃない。適当にもほどがありますよ(笑)
━━(笑)。当時のフジロックの出演者といえば、ビョーク、ソニックユース、ベン・フォールズ・ファイヴ…すごいラインナップですね。
でも、今のキャリアに繋がるのは、大学進学を機に東京に出てから触れたカルチャーです。慶應義塾大学の文学部で美学美術史学専攻という変わった分野で学び、周りも変わった人が多かったです。経済学部や法学部を選んでいたら、違った人生を歩んでいたのかもしれません(笑)。人生逆張りというかアウトサイダー志向がある人間で、そこで培った感性が一番の影響をもたらしてるとは思います。そのころはモグワイやトータス、シガー・ロスなど洋楽ポストロックを聴いていました。
就活に失敗するも、やりたいことができる環境へ
━━いわゆる良い大学からインディーズレーベルへ就職したのはどういった意思決定があったのでしょう?
それは就活に失敗したからです(笑)。僕らの世代は「就職氷河期」の終わりに該当します。編集者を志し、出版社を全て受けたものの選考には受からず、卒業後はアルバイトで生計を立てながらフラフラしていました。
そうした中でたまたま、輸入盤部門を立ち上げたばかりの前職、株式会社インパートメントのアシスタントの求人を見つけました。輸入盤の日本語資料作成をサポートする人員を募集しており、在宅でOKと書かれていたのです。
━━出版社を志していた大崎さんにピッタリで、しかもリモートワークで良いなんて最高ですね!
ところが実際に選考を受けると「フルタイムで出社、いずれ自分のレーベルを持ってほしい」という話で。他にも多数応募は来ていたそうなんですけれど、フルタイムで働けるのが僕ひとりだったようなんです。
━━それは大分話が違いますね(笑)。
でも、19年働いてみて、良い会社だったと思います。2004年にアルバイトとして入社した頃は今ほど社内も整っていなかったのですがそのぶん多くの裁量を持たせてもらえる環境で、当時の上司たちもそれぞれ独立して音楽・カルチャーまわりの仕事をしています。最終的にはみんな独り立ちしてほしい、というメッセージを感じていました。
━━ビジネス環境についても伺いたいです。まだCDが元気だった時代ですが、社内ではどういった目標を立てていたのでしょうか。
目安として国内盤が最低800枚、1000枚という目標があり、たまに輸入盤が1000枚以上出ることもある、という世界でした。そうした環境の中で2005年には正社員登用され、初代の担当レーベルとしてナード・ヒップホップを扱うhueというレーベルを立ち上げ、その後Liricoを立ち上げて徐々にそちらに移行しまして。hueの話は長くなるので割愛しますが…
━━あ、そこ重要なので詳しくいいですか。ナード・ヒップホップってどんな音楽なんでしょうか?
カナダやベルギーのアーティストによるいわば「美しいヒップホップ」で、ポストロックやエレクトロニカのリスナーが聞いていた、すごいニッチなジャンルなんです。とてもメロディアスで、トラックも弦楽器を多用して抒情性が強くて。ラッパーたちもどちらかと言えば歌うようなフロウの人が多かったですね。旋律や構成が美しい音楽を扱うというのは、今やっていることにもつながると思うのですが。
━━今ではすっかりジャンルとして定着したローファイヒップホップに通じる音楽性ですね。
ええ、やることが時代よりも早いんですよね(笑)ローファイヒップホップって、Nujabesが源流になると思うんですけれど、hueで一番売れたカナダのプロデューサーFactorによる「Another Tomorrow」という曲は、Nujabesが亡くなる前にリミックスのお話を頂いたりもしました。実現はしなかったんですけれどね。リリースから17年が経過した今聴いても全く古びていない名曲なので、多くの人にこの曲の存在を知ってもらいたいですね。

プムが日本で爆発することで、昇華される想い
“円が強い時代でしたので、台湾から見た日本のCDの卸値は向こうの市場とはマッチせず、だいぶ値引きして卸さなければいけませんでした。”
Shinsaku Ohsaki
━━では、アジアの音楽を扱うところまでのお話を伺えますか。
2006年に、当時世界の音楽インフラだったMyspaceで色々聞いている中で、オーストラリアの男性シンガーソングライター、タマス・ウェルズの「Valder Fields」を聴いて衝撃を受け、これはちょっとどうしても日本でリリースしなければいけない、という半ば思いつめたような使命感に駆られました。
暗い雰囲気の男性のシンガーソングライターは、そこまで受けが良くない時代です。でも、リリースさせてください、と社内で直談判し、そのためにLiricoというレーベルを立ち上げました。1人1レーベルという中で、異例でしたが。
━━それがすぐさま日本で受け入れられたと。
彼は当時ミャンマー在住で、エイズ教育など地域医療活動に関わるNGOで勤務していながら、音楽を作るというちょっと異色のアーティストだったんですね、そういったストーリーも受け入れられたんだと思います。
彼のリリースを手掛ける中で、中国で暗めの男性シンガーソングライターが受け入れられる土壌がある、と聞き、そこからアジアのマーケットをうっすらと意識しはじめました。
━━第一弾でお話を聞いたmoguさんによると、2002年の北京のインディーズシーンでは男性シンガーソングライターが歌う「アンダーグラウンドフォーク」というジャンルがあったそうですね。
タマス・ウェルズのリリースと並行して、輸入盤を扱うp*disという部門で台湾のWhite Wabbit Recordsと取引ががはじまり、Cicada『Pieces』(2011)の流通も手掛けたことで、台湾の音楽ってこういう感じなんだ、と。
円が強い時代でしたので、台湾から見た日本のCDの卸値は向こうの市場とはマッチせず、だいぶ値引きして卸さなければいけませんでした。今だと別に何も言われないですからね。2010年ごろにはシンガポールのKITCHEN. LABELとの取引もはじまり、欧米のアーティストの中にぽつぽつとアジアのアーティストが混ざってくる、という状況だったと思います。
━━White Wabbit Recordsは日本でも認知されていますが、インパートメントでお取引があったんですね。
2015年にWhite Wabbit Recordsが数年間開催していたP Festivalという、ピアノが中心の音楽フェスティバルにharuka nakamuraが出るというので、帯同で行きました。実際に現場へ行ってみると、台湾のお客さんは若い方が多かったです。その後自分が担当しているピーター・ブロデリックやA Winged Victory For The Sullenが日本と台北でツアーを回すということがあって、台湾のプロモーターはWhite Wabbit Records、日本は僕…と。White Wabbit Recordsを軸に関係性が濃いものになっていきましたね。
-1024x768.jpeg)
━━━それが2017年のLUCfestへの参加とプム・ヴィプリットとの出会いにつながるんですね。
ええ、第一回のLUCfest は、White Wabbit Recordsと音楽イベントの制作を手掛ける9 Kickという団体が共同開催していて予算もあり、日本からインパートメントと数社が招待されていたんです。
━━プムは前もってチェックしていた?
ラインナップの予習をするときに、「Long gone」のMVを観て、変わった音楽、変わったミュージックビデオだなっていう印象です。ただこの時点では、予習した中でピンとくるアーティストのうちの一人でした。
━━その後はライナーノーツに書かれている通り、運命の出会いになったわけですね。
ええ、まず、昼間に音楽業界のカンファレンスがあり、タイの音楽関係者ーーたとえばバンコクのインディー・レーベルで、ライブイベントも制作するParinam Musicやラジオ局のFungjaiーーが出席するプログラムに参加したら、とてもポジティブな雰囲気で、タイの音楽業界ってこんな感じなんだ、という印象でした。
LUCfest自体が第一回目ということもあり、お昼のライブの動員は正直そこまで良くなかったと思うのですが、日が暮れてプム・ヴィプリットの出番になると、ライブ会場に大勢のお客さんが詰めかけていました。そのほとんどが10代後半から20代前半の女性だったように思います。聞いたところでは、数日前にFacebookで「Long gone」のミュージックビデオをシェアしたらかなり反響があったと。
期待に満ちた空気のなか行われたライブは、ギターの弾き語りが6~7曲、ループを使って1人で演奏するというシンプルなセットでした。月並みな表現ですが「見つけた」と思いましたね。この人はすごいことになるかもしれない。そういう直感はありました。
━━それで、ライブ中に、LUCfestの主催者に、この人売れるんじゃない?と話をしたんでしたよね。
その会話の中でWhite Wabbitの方が、「台湾ではうちでリリースとツアーするから、日本も一緒にやらない?」って。それで帰国してすぐ本人に直接メールをしてリリースの話がまとまりました。

-1024x683.jpg)

-scaled.jpg)
━━2018年くらいからいきなりプム無双がはじまったなと思っていたんです。『Manchild』がリリースされる1週間前ぐらいに「Lover Boy」のMVがYouTubeでいきなりバズっていましたよね。
YouTubeのアルゴリズムで、何を聞いていても必ず「Lover Boy」がおすすめされるという状況で。『Manchild』のプレスリリースを送ったときにWWWの方が気に入ってくださり、リリース直後の4月にアジアと日本のバンドの交流を促進するイベント「In & Out」への出演が急ピッチで決まりました。その後同年の12月に2回目の来日。日本で受け入れられていく姿を、一番近くで見ることができました。
━━プムが大きな存在になることで、大崎さん自身に変化はありましたか。
それまではリリースを手掛けたアーティストは、招聘、帯同など、全ての工程に自分が関わるということをしていました。実家にアーティストを泊めたことも一度や二度ではありません(苦笑)それが、プム・ヴィプリットを手掛けることで、「影響力のある方々が担当アーティストを呼んでくれる」という状況になったのが大きな変化でした。
あとはプムとの仕事でアジア人としてのアイデンティティを初めて実感しました。欧米のアーティストをリリースしている時には感じたことがなかったことで、アジアのアーティストを日本に紹介する仕事はそれまでとは違う楽しさがありました。
僕自身は、社会人になってから「大型フェスに行くときは自分の担当アーティストが出るとき」というマイルールを持っていたのですが、2019年にはSUMMER SONICへの初出演も決まり、「そろそろ会社を辞めようかな」という、うっすらとした思いが確信に変わっていったんです。
“家庭内のバランスが不釣り合いなことがずっと気になっていて”
“リスナー側の価値観が徐々に更新されることで、洋楽と邦楽の垣根が融解していくと思います”
“何者でもない自分が、アーティストを通して何かを成し遂げた。そういった瞬間が19年間でいくつもありました”
“この記事を読んでいる若い方で、僕にとってのタマス・ウェルズやプムのようなアーティストがいたら、助けてあげてほしいと思います”
担当アーティストの、日本で一番のファンは自分
━━あらためて、大崎さんの仕事のポリシーを伺えますか。
シンガーソングライターでよくある、作詞・作曲・演奏・録音までの流れを全て自分でやるというスタイルに憧れを持っているので、レーベル業においてもなるべく自分で全て対応するという考えでやってきました。ですので自分でライナーノーツを書くことも多く、唯一無二の内容が書けていると思います。歌詞の対訳まで自分でやったりとか。
━━色んな人を巻き込んだ方が広がりがあるという方もいます。
ええ、なので自分が正しいとは思っていないのですが、自分がレーベルをやって日本でせっかくリリースをするので、そのアーティストの日本での一番のファンは自分でありたい、という気持ちでやってきました。極端な話、自分の大切な友人とか家族に対して、紹介するみたいな気持ちでいたいと。そのスタンスを入社してから19年間の間、最初から最後まで貫き通すことができたと思っています。
━━ではそれらの経験をベースに、いよいよ一旗揚げようという主旨の独立でしょうか。
いえ、そんなにカッコいい理由ではないんです(笑)2015年に結婚して、共働きなのですが、どうしても働き方や収入、家事の比率など家庭内のバランスが不釣り合いなことがずっと気になっていて。
━━よりよい生き方を求めて、ということなんですね。
妻は僕の仕事を理解して、アーティストとも友達になってくれるような懐が深い人なのでありがたいのですけどね。インパートメントのスタッフではないのに物販の販売も率先してやってくれたりしていつも助けてくれました。
2018年ごろからうっすらと退職を考えていたのですが、プムという才能との出会いが延命してくれており、それでも、プムのセカンドアルバムをリリースしたら終わりにしようと思ってたんですけど、2020年くらいに出る予定だったアルバムがコロナの影響で延びに延びて、やっと今年出たので終われたという(笑)仕事を徐々に整理していく中で、2022年にはSUMMER SONICに2回目の出演をしたし、もう思い残すことはないな、と。


━━今、足元ではどういったことをやっているのでしょう?
インパートメントとは円満退社なので、印税などの管理業務や、これまでLiricoレーベルでリリースしてきたアーティストのニューアルバムが出るときには、製作請負という形で関係が続いていきます。それ以外の空いた時間で、自分のやりたいことを拡大していくイメージです。プムやタマス・ウェルズという、これまでの長い付き合いがあり、真に愛情を注げるアーティストを大切にしたいと思っています。同時に、彼らを超える新しい才能に出会いたいなっていう期待もあります。
━━これまで19年というキャリアの中で、洋楽を扱う視点からアジアのバンドを見てきた大崎さん。若い方にアドバイスできることはありますか。
いま、楽曲リリースやPR、ファンとの交流まで自ら幅広くこなせるアーティストが増えて、レーベルの必要性が薄まっていると思います。レーベルを通さず直接ストリーミングで楽曲をリリースする手段や選択肢も増えてきましたしね。プムは英語が堪能なこともあり、アルバムリリースや契約のやりとりなどもレーベルを通してではなく、僕と直接やっていたんです。
それでもやはりアーティスト1人でできることには限界点があるんですよ。
━━人間ですものね。
そこに、大きな輝きを放てるわけではない、いわば何者でもない自分が、アーティストを通して何かを成し遂げた。そういった瞬間が19年間でいくつもありました。アーティストを助ける人材は絶対必要なんですよね。国境を越えるならなおさらです。
これを読んでいる若い方で、僕にとってのタマス・ウェルズやプムのようなアーティストがいたら、助けてあげてほしいと思います。
━━日本でアジア音楽を発信してる方々の思想って色々ありますよね。日本が取り残される危機感を強くお持ちの方もいれば、費用対効果を求めて淡々とやってる方も、自分の信じるアーティストを出していくみたいな方もいる。
僕はその3つだと、全て当てはまります。BiKN Shibuya 2023はまさに危機感へのアプローチですよね。そうした中で、アジアのアーティストの皆さんはすごくフラットで、さまざまな境界を飛び越えて、どんどんコラボレーションして…という状況の結果、今のシーンが生まれています。Sobsのメンバーが数年前に言っていましたが、東南アジアの若者たちはわざわざ欧米に目を向けなくても、自国にも良質な音楽を奏でるアーティストがたくさんいるということに気づき始めていると。日本のリスナーももっとそのことに気づいて欲しいですね。
━━10年後、日本でアジアのアーティストはどんな扱いになっているでしょうか?
今のところ洋楽と邦楽の垣根という分類がどうしても存在すると思っています。台湾のバンドは中国語で歌ってるので、音楽性はロックでもワールドミュージックの棚に置かれちゃう、ということですね。
ただ、リスナー側の価値観が徐々に更新されていますので、この垣根は融解していくと思います。10年たたないうちに、大きな変化が訪れるんだろうなっていう。

━━最後に、大崎さんが一番やりたいことを教えてください。
自分が企画・招聘をしたライブでも、終わった後にお客さんが「〇〇のライブ、めちゃくちゃよかった」とか「最高の時間だった」とSNSで感想を書いてくださることがあります。それを読んでは、「あぁやってよかったな。報われたな」って思うんですが、1週間後にはみんなその時の感動を忘れて日常に戻っている。これだけ情報が溢れる中では仕方のないことかもしれませんが、それはどんなライブでもよくある話ですよね。
ただ、それと同時に一見忘れてしまっているように思えても、それこそ10年くらい経って、ふとした瞬間に「10年前に見たあのライブ、本当によかったなぁ」と、少しでもライブのことを憶えてくれている人がいてくれたらいいなって毎回思っています。だから自分で招聘するライブは、会場についてもこだわっています。タマス・ウェルズであれば、2007年の初来日は金沢の21世紀美術館でやりましたし、他にも光明寺や、自由学園明日館、旧グッゲンハイム邸、早稲田奉仕園のスコットホールなど10年後に憶えておいてもらうための努力はしてきました。ライブは即効性が求められるものかもしれませんが、そこに遅効性が加わることで音楽の力が真に発揮されると僕は思います。
━━ありがとうございました。そして、あらためて、独立おめでとうございます!
Follow & Information
大崎さんがアジア音楽のキャリアを築く原点となったアーティスト!
20年変わらない「天使の歌声」
シンガーソングライター タマス・ウェルズ待望のニュー・アルバムが6年ぶりにリリース!
タイトル: To Drink up the Sea(トゥ・ドリンク・アップ・ザ・シー)
<トラックリスト>
1. It Shakes the Living Daylights from You
2. Arguments That Go Around
3. Every Other Day
4. It’s Not the Same
5. Tooth and Nail
6. August I Think Nothing Much at All
7. A Little Wonder
8. Shells Like Razor Blades
9. The Tattoos on Anna’s Feet
10. To My Love
価格:2,400円(税抜) / 2,640円(税込)
発売日:2023年12月8日(金)
レーベル:Lirico(販売元・発売元:株式会社インパートメント)

ソングライター、タマス・ウェルズ。6年ぶり、通算7作目となる待望のニュー・アルバムがリリース。
コロナ禍と父の死を乗り越えてようやく完成させた本作『To Drink up the Sea』は、ベースとドラムを初めて本格的に導入したアルバムとなった2017年リリースの前作『The Plantation』でのエヴァーグリーンなバンド・サウンドを踏襲しながらも、また新たな音楽的領域に踏み込んでいます。
タマスがかねてから大ファンだった、オーストラリア人シンガー・ソングライター、マルチ・インストゥルメンタリストであるマシーン・トランスレーションズことグレッグ・J・ウォーカーをプロデューサーに迎えて製作。ピアノとアコースティック・ギターを基盤にしたオーガニックなアコースティック・サウンドに、ウォーカーによってもたらされたチェロ、ヴァイオリン、マンドリン、クラリネットなどさまざまな楽器による豊潤なアレンジが長く耳に残りつづけます。
先行シングルとなった「It Shakes the Living Daylights from You」が特に顕著ですが、タマス・ウェルズ最大の武器である中性的な美しい歌声の多重録音ハーモニーと、グレッグ・J・ウォーカーならではのソフト・サイケデリック・フォークが融合した新境地は抜群の中毒性があります。
アルバム・タイトル(「海を飲み干すこと」)はドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの著作からの一節。「もし私たちが”海を飲み干す”なら、その中で航海することができるのか?」と、「神の死」を提唱したニーチェの虚無主義から彼が感じた抽象的な問いかけはタマス・ウェルズが書く歌の本質でもあります。
一度心を奪ったものを恒久的につなぎとめるその歌声は、タマス・ウェルズというアーティストが初めて世に現れてから20年近く経った今もその特別さは何ら変わっていません。